これからM&Aで会社を譲渡しようと考える売主が、
「この人はよく会社に来てくれてやる気も感じられるので仲介を依頼しよう」
といった理由でM&A仲介会社を選ぶケースは意外と多いです。
ですが、こうした理由で選んで結果裏切られたと感じている方は結構多いのも事実です。
M&Aコンサルタントはやる気だけではどうにもならない、と言ってしまえばそれまでですが、ここにはきちんとした理由もあります。
ここでは、M&Aコンサルタントをやる気だけで選ぶリスクについて記載します。念の為ですが、売主がどういう理由でM&A業者を選ぶかは自由ですので、こうすべきと述べるつもりはなく、色々な観点で業者との接点を考えていただく機会にしていただければという趣旨で記載しますのでご理解いただけますと幸いです。
なぜM&Aコンサルタントをやる気で選ぶと失敗するのか
これまで全く取引をしたことのない事案に対して専門業者を選ぶとき、頑張ってくれそうな業者を選ぶことはよくあります。
どの業者が良いかなんて定量的に判断できないことも多いため、「やる気」というどんな業界・業種でも共通している判断軸で選ぶわけです。
もちろんやる気があるというのはとても大事なことではあります。
M&A仲介については、買手を見つけてくるという業務も含まれるため、やる気が無くて全然候補先の提案が無いとなれば、M&Aの実現などできるわけがないと思ってしまう方も多いでしょう。
ただ、ここには落とし穴もあります。
酷いケースでは、売主側が「仲介会社に騙された」と感じることさえあるのが昨今のM&A業界の闇と言えるでしょう。。
それではどんな落とし穴があるでしょうか。
以下に、よくある「M&Aコンサルタントをやる気で選んで失敗した事例」について取り上げてみたいと思います。
・やる気だけで、専門家として基本的な知識が無い
・担当者はやる気があるのに、なぜか話が先に進まない
・よく考えたら手数料が高い
着手金を支払った途端、担当者のやる気が無くなった
M&A業者の中には着手金を徴収する業者もいますが、そういった業者を利用する際で発生するリスクのあるトラブルです。
売主としては仲介契約を結ぶ前までは熱心に訪ねてきたため信用できると思い、仲介者として起用を決定するとともに、着手金を支払ったものの、それからは動きが遅いか動いているかどうかすら分からないという状態になってしまったという事例です。
仲介会社の中には、コンサルタントに受託件数や売上のノルマを設けている会社もあり、さらに、成果に応じて賞与などといった形でインセンティブを渡している会社もあります。
担当コンサルタントが始めからその案件を成約させるつもりなどなく、着手金や受託件数のノルマを達成するために熱心に動いていたとすれば、その目的が達成した時点で意欲が下がってしまう可能性もあります。
通常は、成約時の成功報酬に比べれば着手金の金額は割合として低いため、着手金があるM&A業者でも成約を目指すインセンティブは依然としてありますが、中々決まりにくい案件(財務状態が著しく悪い、売主の希望条件が著しく高い、様々な問題を抱えている、など)というのも世の中には存在しますので、そうした案件について着手金を取る目的で近づく業者が無いとは限らないということも覚えておきたいポイントとなります。
やる気だけで、専門家として基本的な知識が無い
M&Aコンサルタントとして経験が浅い者の場合、知識や経験が無い分、やる気でカバーしようとするというケースはよくあります。
未経験で入社を受け入れているような仲介会社では、組織の中に経験豊富なコンサルタントもいればそうでないコンサルタントもいるため、営業戦略上、経験の無いコンサルタントは売主に気に入られて懐に入り込むことに特化して、専門的な話は社内外にいる専門家に聞きながら案件対応する、という体制を取っているケースもあります。
担当コンサルタントに専門家としての知見が無い場合、毎回些細な事でも都度確認をしてコミュニケーションにストレスがかかることも有りますし、場当たり的で適当なアドバイスをされたりということも出てきます。
M&Aのディールというのは非常に繊細で、言葉選び一つ間違えたことで破談になるということもあります。
担当者のやる気はあるし憎めないけど、知識が無くてM&Aを進めることについては頼りがいが無い、という場合には、たとえいいなと思える買手候補と交渉の場についたとしても突然梯子を外されるような破談となるリスクがあることは気にしておくとよいでしょう。
担当者はやる気があるのに、なぜか話が先に進まない
担当者はフットワークが軽く、レスも早いのに、全然話が進まず、売主のフラストレーションがどんどん溜まっていくというケースもあります。
これは、仲介会社内の仕組みが原因であることもあります。
仲介会社によっては、売手担当・買手担当、ソーシング担当・マッチング担当・エグゼキューション担当、などといった形で担当分けされていることもあります。そのため、売主がこれまで話している売手担当やソーシング担当はやる気があるのに、買手担当やマッチング担当がサボっているため一向に買手が見つからず案件の進捗が止まってしまうといったケースです。
売手側の事情とは関係なく、買手担当やマッチング担当としては、できるだけ早期に成約できる見込みのある案件に工数を割いた方が、効率が良いと考えるのは自然でもあるので、早期に成約できないと見做された案件は放置されるなんてこともあります。
全部同じ担当が一気通貫で担当していればこうしたモチベーションの差は出ないので、選ぼうとする仲介会社で担当制を取っているかどうかの方針については事前に確認しておいた方がよいです。
よく考えたら手数料が高い
M&A業者の手数料は各社自由に設定できる仕組みになっています。
そのため、各社の仲介手数料をきちんと比較して比べないと、倍以上の高い手数料を支払う仲介契約を結んでしまっていたなんてことも良くあります。
やる気が一番ありそうだからとあまり仲介手数料に拘らず仲介会社を選んだ結果、実際にはきちんとサポートしてくれないことが後から分かり後悔するというケースも多いように思われます。
手数料の話を前面に出すと選ばれにくい仲介会社は手数料以外のアピールポイントを強調するものですし、逆もしかりです。各社どのようなアピールをしてくるかを見ることで冷静に比較することができるようになるので、その観点ではできるだけ多くの仲介会社を比較検討することは重要と言えます。
以前、以下の記事で仲介会社の手数料を比較したものがございますのでご参考いただければと思います。
ちなみに、担当者から「仲介手数料が高くてもその分高く売ってくるなら問題ない」という説明は受けていないでしょうか?
M&A仲介は利益相反の関係上、買手に対して高い買収金額を交渉して勝ち取ってくる、といった機能はありません。
そういったことをしている仲介会社があればM&A中小ガイドライン違反ですし、営業上のリップサービスであってもそういったニュアンスで売主が受け取ってしまっている時点で問題です。ガイドラインの内容を把握していない仲介会社やコンサルタントに任せることは一番危険ですので注意しましょう。
一度仕切り直したいと思ったら
最初は良いと思ったけど、やっぱり他の仲介会社の方がよいかなと思った場合どうしたらよいでしょう?
もし、具体的な買手候補先と具体的な交渉に進んでいないのあれば、一度仲介契約を解除するという手段があります。
前述の通り、買手探しの体制についても問題がある場合もあるため、いつまでも同じ仲介会社に依頼し続けていると何も進まず時間だけが過ぎていってしまうということにもなりかねません。
仲介会社としては、特に受託している状態を維持し続けたとしても特にコストが継続して発生し続けるわけではないですし、いつかその会社を買いたいという買手が現れる可能性がゼロではないですし、会社によっては受託件数の残高が将来的な収益への期待値として対外的にアピールできることもあるわけです。
そういう事情があると、仲介会社としては受託の状態を引っ張っておいた方がメリットがあるとも考えたりします。そのため仲介会社から自発的に仲介契約を解除したいという話にならないことも多いのです。
契約書上、他の仲介会社と仲介契約を結んではいけないなど売主が拘束され続けることにも繋がるので、売主側から解除を申し出るのがよいでしょう。
「着手金を払ってしまっていてそれがもったいないから」
という理由であれば、個別の交渉で着手金が取り戻せないか、なども検討するのもよいでしょう。
明らかに仲介の仕事をしておらず着手金を取られただけ、という売主でも契約している仲介会社に掛け合ったものの返金を拒否されたという話も聞きますが、弁護士を通じた話し合いとしたり、その仲介会社に話を通せる方経由で掛け合い返金させたという話もあったりします。
また、仲介契約解除にあたり、過去仲介会社が打診先した先全てと今後数年間M&Aを実現させたら仲介契約書上の成功報酬が発生します、といったようなテール条項を解約後も有効とする話が上がるケースもよくあります。
テール条項としては、そもそも契約期間終了後の取決めに関するものではありますが、ここでの注意点としては、本当に仲介会社が打診したのかどうか、具体的な話し合いがなされたのかといったことが売主には分からないため、解除する仲介会社の言い分を真に受けると売主が契約解除後も過度に拘束され続けるということにもなりかねないということです。
当社ではこういった他仲介会社との契約解除についてもご相談を受けるケースがありますが、過度な要求なのかどうかは同業目線での考え方をお伝えするようにいたします。昨今では、中小M&Aガイドラインも強化されていく傾向にはあるので、ガイドラインと照らし合わせてみてどうかという視点も持ちつつ対処していくことが必要です。
当社では、他のM&A会社様でお話を進めておられる会社様からも、セカンドオピニオンとしてご相談を承っておりますので、お困りの際にはお気軽にお問合せいただければ幸いです。
お問合せの際には以下のお問合せフォームよりお願いいたします。
お問合せ
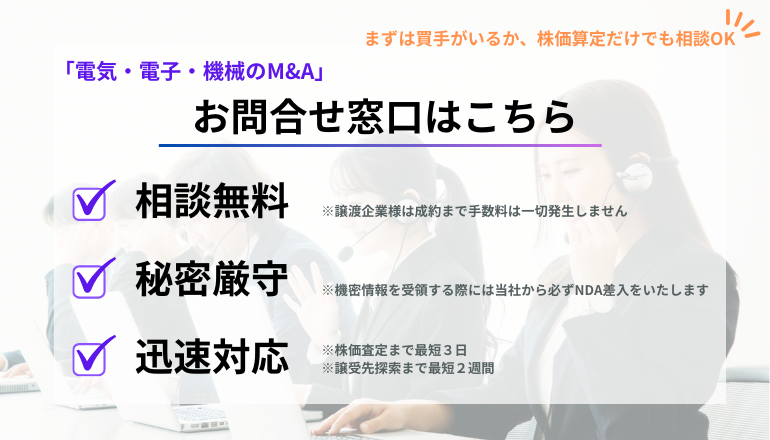
-2.png?1764541836)
.png)