近年、中小企業のM&Aが盛んにおこなわれています。
そのため、ある日突然、仕入先から、
「M&Aを考えているんだけど許可してくれるか?」
というおうかがいが来ることもあります。
反対した時にどうなるかも想像できないことも多いので、甘受することもあるかもしれません。
でも、よくわからない会社へ譲渡されてしまうことで今後の供給が不安になったり、対応が悪くなってしまう可能性があるのであれば容易に甘受けすることもできないこともあります。
今回はこのような時に購買・資材調達側はどうすべきかを考えてみたいと思います。
M&Aの阻止というと敵対的買収を阻止する方法論に関する記事が多く、また、どちらかというと中小企業のM&Aが上手くいく方法(M&Aを後押しするような内容)を伝える記事は多いですが、この記事を検索されている方はそういう視点ではないと思いますので、購買・資材調達目線で考えてみたいと思います。
当社はM&Aを支援する会社ではありますが、とにかくM&Aさせるように煽るような伝え方はせず、現実的に起こり得る問題を取り上げて関係者含めて納得のいくM&Aをしていただきたいという想いからこういった内容も取り上げております。ご参考いただけますと幸いです。
何の前触れもなく訪れる「M&Aしても良いか」
購買・資材調達側に仕入先のM&Aの話が来るときは、「ある突然」ということも結構多いです。
また、場合によっては、「事後報告」ということもあるでしょう。
まずこの通知に関して、当事者サイドでどういう話になっているかを見てみましょう。
仲介者の進め方によっても異なりますが、概ねこういった整理をしています。
・売主の個人的な想いから、得意先と話をした上でM&A検討をしたい場合
→比較的早い段階で購買・資材調達側に相談がくる
→M&Aの最終契約締結後クロージング前に購買・資材調達側に相談がくる
→M&A後に報告のみ行うことも有り
例えば、仕入先の売上高の内、90%以上が1社の得意先に集中しているようなケースでは、M&Aの検討を始めるにあたって、「もしこの得意先がM&Aに反対したら、売上がほとんど立たない会社を買収することになってしまう」という可能性も考え、早い段階で得意先の購買・資材調達側におうかがいを立てた上で、M&A検討を始めようというケースもあります。
本来、検討初期の段階でM&Aを検討している意思を明らかにすることは、M&Aの売手側にリスクがあるものですが、M&A終盤になって話が全部ひっくり返るというインパクトも考えると妥当な判断と考える当事者もいます。
M&Aの買手側からすると、売上の大半を失う可能性のある会社を買収しようというのは普通に考えてリスキーですので、売却企業の従業員だけ欲しいというような特殊な理由でもない限りは、「最初に主要な得意先とは話をつけておいて欲しい」と思うものです。
ただし、検討初期の段階では、買手も定まっていないこともあるでしょうから、仕入先から「M&Aを許可してくれるか」と聞かれたとしても、それに回答できるだけの判断基準もない、ということもしばしばです。
一方、M&Aの終盤あるいはM&A後に購買・資材調達側に連絡がくるケースというのは、「買手がM&Aするまでに得意先の許可が得られれば良い」というケースか、「最悪取引が無くなってもM&Aを辞めるほどではない」というケースと考えることもできます。
得意先と仕入先の間では、取引基本契約書のような、取引についての包括的な取決めを定めた契約書が存在することもありますが、場合によっては「CoC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)」という定めがあり「もしM&Aなど経営権が異動した場合にはこの取引基本契約書は無効になるよ」という旨が定義されていることがあります。
この、CoC条項には、強めのCoCや弱めのCoCというような匙加減があり、「通知すれば足りるもの」もあれば、「M&Aする前に書面で許可を取らないとダメ」というものも有ります。
M&Aを行う前に、M&Aの買手が売手企業に対して買収監査を行いますが、当然そこでは取引先との契約書にも目を通しますので、このCoC条項にも気付くことができ、事前に許可がいるようなものであれば、最終契約書で「M&Aを実行する前までに取引先にM&Aの許可をもらうこと」といった趣旨の条件を売手に対して付します。
事後に通知だけすれば良いケースや、取引基本契約などなく、都度注文書で取引しているようなケースで、万一取引が消失してもM&Aを行う上での投資判断に大きな影響を与えないという場合には、M&A後に購買・資材調達側に連絡が来るということもあります。
つまり、まとめると、
・取引喪失のインパクトや契約書上の取決めによって話の上がり方が異なる
ということです。
仕入先のM&Aを阻止できるの?
ここで本題です。
もし、購買・資材調達側が、「この相手とはM&Aしてほしくない」と思った時はどのような手段が取れるでしょうか?
大きく分けてこのようなこのような選択肢があると思います。
・CoC条項等の取決めが無い場合でも、容認できない理由を伝え諦めてもらう
意図せぬ会社に買収され、現行の取引契約が他社に流用されるのを防ぐ目的でもあるCoC条項があるのであれば、それに則り手続きをすれば良いです。また、そういった取決めが無かったとしても、得意先が許可できない合理的な説明をしつつ、M&Aを行うことについての懸念を示すことは何ら問題ありません。
一点、注意すべき点としては、得意先と仕入先の関係性や状況によっては、「M&Aをするなら取引を打ち切る」といった伝え方や、「コストダウンするならM&Aを許可してやる」といった伝え方となると、独占禁止法違反や下請法違反などへの抵触も注意した方が良いため、伝え方には配慮が必要です。
もっとも、M&Aというのは売手と買手の取引であって、主要な得意先であってもその経営判断に口出しできませんので、得意先の立場で「断固拒否!」と主張したところでM&Aを止める直接的な強制力にはなりませんし、売手も買手も得意先との取引消失も覚悟しての話であれば、結果として取引が無くなるだけです。ここで得意先ができるのは、M&Aを強行すれば取引が無くなる、あるいは、明らかに取引量が減るという可能性も踏まえてどうするか?と相手に再検討してもらうこと(ボールを投げ返すこと)です。
M&Aの買手にきちんと供給体制を引継ぐ旨を説明してもらう、といったことで得意先側の懸念が低減できるような話であれば、「今後引継ぐM&Aの買手に説明してもらいたい」と依頼するのもよいでしょう。また、一旦取引契約書は解除し、再度新しい買手のもとで新しい取引契約書を巻き直す、というケースもあります(事業譲渡の場合は基本的に巻き直し)。
ちなみに、実務的にはM&Aの買手が売手に対して、「現行の取引量が維持できないならM&Aしない!」という強めの要求があるのであれば、売手である仕入先から購買・資材調達に対して、「M&A後も従前の取引を行う」ことを約束する合意書に署名してほしいという感じの強めの依頼になることが多いので、これに反対する購買・資材調達は合意書に署名しないという手段もあります。
こうなると、合意書が提示できない以上、M&Aが成立しないか、あるいは、M&Aの買手が譲歩するか、M&A条件を緩和(合意書が無い替わりに譲渡金額を引き下げる、など)をして無理矢理M&Aを成立させるか、という展開になっていきます。
購買・資材調達側としては、最終的な結末が100%読めないやり取りにはなりますが、仕入先において特定の得意先への依存度が高ければ高いほど、その得意先の反対によってM&A自体が頓挫する可能性が高くなる、と思っていて相違ありません。
予期せぬ仕入先の行動に先駆けてやるべきこと
得意先の購買・資材調達としては、こういった仕入先のM&Aは面倒なことかもしれません。
また、M&Aを検討することも無く、いきなり仕入先の社長が倒れて廃業する、ということもあるかもしれません。
こうした予期せぬ仕入先の動きに対応するためには、予めCoC条項を盛り込んだ取引契約書等を締結しておくのが有効です。
また、それだけではなく、M&Aの前兆を把握するには、日々、担当者だけでなく、経営者とのコミュニケーションもしておくことがよいでしょう。
賀詞交歓会や表敬訪問、接待のお誘いなどどの程度頻繁に経営者が前に出てくるかも見つつ、高齢な経営者であれば事業承継などについてどうするつもりか探っておきましょう。「最近M&A会社の営業多いですよね?」「最近取引先のM&Aの申し出が多くて・・」と軽く触れるだけで、自ら色々と喋ってくれる仕入先社長もいます。
M&A仲介会社というのは会社を売りたい人にダイレクトに営業することが多いですし、会社を売りたい人とて、M&Aの相談は、得意先ではなく、顧問税理士や取引銀行や公的機関などにすることが多いです。
それゆえ、得意先が認知しないところで、M&Aの検討が進んでいってしまい、ある日突然仕入先のM&Aの話が持ち上がる、ということになりかねないです。
急なM&Aの話で困惑しないよう、仕入先との密なコミュニケーションに心掛けましょう。
もし、もうM&Aしたい旨の連絡が来ているのであれば、M&Aの全容を把握した上でしかるべき判断をする必要があります。ここから得意先の意図する他の会社とM&Aしてもらう、という話法も無い訳でないですが、きちんと状況を整理して慎重に対応しましょう。
「仮に仕入先がM&Aの悩みを持っていても過干渉できないし・・」と思われる得意先様向けに、当社では、得意先も関与した上での仕入先移管・統合をサポートするサービスも提供しておりますので、無料相談からお気軽にご相談下さい。
お問合せの際には以下のお問合せフォームよりお願いいたします。
お問合せ
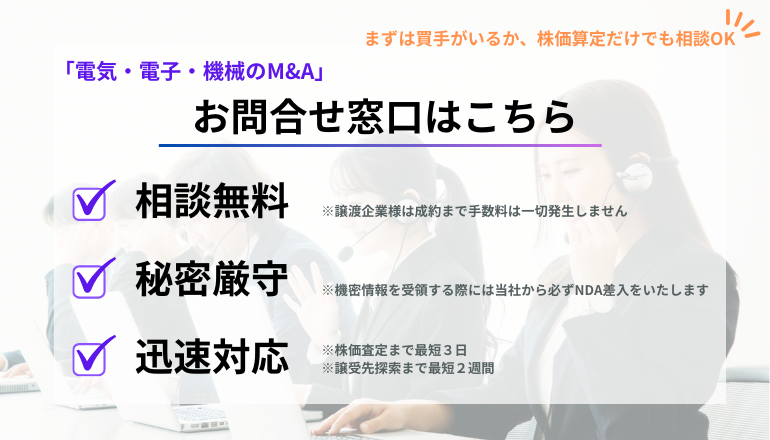
-2.png?1756604074)
