最近では、ネット上にM&A関連の情報が充実してきたこともあり、自力でM&Aによる会社・事業の売却に取り組む方も増えてきているように思います。
「ネットの情報よりも経験値のあるコンサルタントの意見を聞きましょう!」
というのが、M&A業者のセールストークですが、巷では「M&A業者に紹介された買手とM&Aして詐欺に遭った!」とか「本当にM&Aについての知識や経験があるのか怪しい担当者だった!」といった声もあり、逆にM&A業者を使うのってリスクなんじゃない?という方すらいます。
これ、あながち間違っているとも言い切れないところがあります。
M&A業者のコンサルタントというのは成約のノルマを抱えているので、何としても押し込んで成約させよう、と変なバイアスがかかったアドバイスをしてくる者もいるのも事実。
それゆえ、業者・コンサルタント選びに失敗すると、M&Aが上手くいかないだけでなく、穴だらけのM&Aをしてしまい、せっかくM&Aをしたのに枕を高くして寝られない、なんてことになりかねません。
あと、ネットの情報といっても侮ることなかれ、今やM&Aフォローの細部に至るトラブルシューティングに対応できるほど充実してきていますし、生成AI技術も発達してきているので、特定の仲介会社が発信するポジショントークまみれの情報に惑わされることなく、疑問点に対する回答を得ることもできるようになってきています。
「じゃあ、M&A業者なんてもういらなくない?」
という話ですが、では業者を使わずにM&Aをするということが難しい場面もありはするので、今回はそのあたりの話題に注目してみます。
この手の話は、執筆しているのがM&A業者の立場だと「積極的に仲介会社を使いましょう」という論調になりがちですが、この点についてはポジショントーク抜きでお伝えできればと思います。
M&Aは自力で行う方法もある
M&Aで会社を売却しようとするとき、普通は右も左も分からないので、自力でM&Aしようといってもまず何をしたらいいか分からない方もいると思います。
誤解を恐れずにいうと、売手の場合、究極的には買手さえ見つけられれば、あとは買手から要求される資料類を用意して、真摯に対応しつつ契約締結まで行うことも可能といえば可能です。
売手として必要以上にリスクを負わないようにしたり、もっといい条件を買手から提案してもらう、といった目的があるから事前に作戦を立てるわけであって、この辺を無視するなら買手が見つかれば取引自体はできる可能性があります。
「じゃあ、どうやって買手を探すの?」
という話ですが、AIに聞いてみても割と正確な回答をくれたりします。
Q:M&Aで会社を売却しようと思っているんだけど、買手ってどう探したらいいの?
A:会社の売却を考えるとき、「誰に買ってもらうか(買手探し)」はとても重要です。買手によっては価格も、会社の今後も大きく変わります。以下に、買手の探し方を段落ごとに分けてわかりやすく解説します。
① M&A仲介会社を使う(最も一般的な方法)
多くの中小企業オーナーが利用するのが、M&A仲介会社(M&Aブティック)を通じた買手探しです。仲介会社は、売手と買手の間に立って、条件交渉や資料整備、マッチングまで行ってくれます。買手候補を既に多数持っているケースが多く、効率よく話が進むのがメリット。ただし、仲介手数料(成功報酬など)はそれなりにかかりますし、「売手と買手の間に立つ」という立場上、完全に売手寄りというわけではない点に注意が必要です。
② M&Aプラットフォームを使う(自力でも探せる)
近年は「M&Aプラットフォーム」というネット上のサービスも増えており、売手が自社情報を掲載して、買手と直接コンタクトを取ることもできます。代表的なものに「TRANBI(トランビ)」「Batonz(バトンズ)」「M&Aクラウド」などがあります。比較的手数料も安く、自分のペースで進められる一方、買手とのやりとりや条件交渉はすべて自分で行う必要があり、専門的な知識がないとリスクもあります。
③ 自分で業界内・取引先にあたる(スモールM&A向き)
業界内でつながりがある会社や、既存の取引先に対して直接「事業承継や売却を検討している」と打診するケースもあります。すでに信頼関係がある相手だと話が早く進む可能性があります。ただし、情報の取り扱いには細心の注意が必要で、うわさが広がってしまうリスクもあります。基本的には、秘密保持契約(NDA)を結んでから進めるべきです。
④ 専門家(税理士・会計士・FA)経由で探す
普段から付き合いのある税理士、会計士、またはフィナンシャルアドバイザー(FA)が買手候補を紹介してくれることもあります。中には企業のM&Aを専門とする士業やコンサルもおり、中立的な立場でアドバイスしてくれるため安心感があります。報酬体系や支援範囲は事前に確認しておくとよいでしょう。
⑤ 買手からのアプローチ(意外とある)
場合によっては、あなたの会社に興味を持った買手の方から「会社を売る気はありませんか?」とアプローチされることもあります。特に成長中の業界やニッチな分野の企業であれば、買手側から積極的に探してくることも。こうしたオファーは突然来ることが多いため、すぐに動けるように「売却の最低条件」や「希望条件」は頭の中で整理しておくと安心です。
もしご希望があれば、あなたの会社の業種や規模感に合った「買手の探し方の戦略」を一緒に練ることもできますよ。どんな業界の会社か、ざっくり教えてもらえたら最適な方法を提案します!
デメリットや注意点まで教えてくれており、下手すると新米コンサルタントが回答するよりもたぶん正確で網羅的なのではないかと思うくらいのクオリティです。新米コンサルタントが憶測で喋るタイプだったら、もはや比べるまでもないです。
何か疑問点があり、それを解決するために自分で色々と調べられる方は、実はM&Aの手順や手続きについてあまり詳しくなくとも結構な部分を自力で行えてしまうということはあります。
チャットGPTの初期に少し触ったよ、という方の中にはAIの回答に半信半疑の方もいるかもしれませんが、AI分野ではRAG技術なども進化しておりハルシネーションの解消が急速に進んでいます。つまり、ひと昔前よりも真実性・正確性が高い回答が得られるようになってきたということです。
高い仲介手数料をわざわざ払ってM&Aするのではなくて、調べながら自分でやってみようというのもそれはそれで合理的な判断と言えるでしょう。
M&A会社を使わないと何が困るのか
それでは、M&A業者を使わずにM&Aを自力で進めた時、どんなことが困るのでしょうか?
M&A業者は、最初から「自力でやるなんて無謀だ」という立場で喋ることも多いのですが、何が自力でできて何が自力では難しいのか、は切り分けた方がいいと思います。
自力で難しいことの一例ではありますが、例えば、以下のようなことに困ると思います。
1.買手探しで行き詰る
まず、何が困るかというと買手探しです。どうやって探したらいいか分からないはずです。
実際、M&A業者が売手から委託を受けて買手を探すのだって苦戦することも多いのに、自力でというのは難しくて当たり前です。
方法としては、まさに前述のAI回答のような調べ方にはなるのですが、もっと突っ込んで、M&A仲介会社や専門家がどうやって探しているかといえば、自社で候補先を選定して交流のある先であれば担当者に聞く、交流が無い先だけどこの会社なら買収するのではないか、という先にはドアノックして確認することもあります。
ここで、「この会社なら買収するのではないか」と見立てることが経験の無い方の場合難しいのです。
例えば、ただ同じ業界の大手だからって理由だけで打診しても、大抵けんもほろろな対応をされます。まず買収を検討する会社かどうか、次に、投資対象になり得るかを判断する必要があります。
そのためには、M&A業界の動きも把握する必要がありますし、提案する投資対象として適切か、客観的に売却する自分の会社を分析できないといけないです。
候補先について仮説を立てて、打診をして、思うような結果にならなかったら、候補先を洗い直して再度打診・・ということをしていく必要があるのですが、これを自力で行うのは大変だと思います。M&A業者の強みとしているのは、「この案件をこの買手に持っていったらこういう反応されるだろうな」という想像力とも言うべき部分であり、これは大量の買手打診とそれによって得られたフィードバックを経験値としてもっているかどうか、なので、M&A業務をしたことが無いと難しい部分があります。
結局、能動的に買手に打診しに行くというより、M&Aプラットフォームに登録して、ひたすらオファーが来るのを待つという受け身の姿勢での買手探しになる方が多い気がします。
2.買手の要求が妥当かどうかが分からない
M&A業者を使わずに買手と交渉する場合、買手が言ってきた要求がだろうなものなのか分からない、という現象が起きます。
初めてM&Aを行うのであればこれは仕方のないことで、買手が言ってくる要求が、M&Aをするのであれば当たり前のレベルの内容なのか、普通の買手なら言わないような無理な内容なのか、区別がつかないのです。
この区別がつかないと、M&Aをするなら当然出さないと話が進まない情報なのに売手が出すことを拒み、「この売手気難しいな」「これ以上M&A検討進めるの難しいな」と買手に思われてしまい、ある日急にM&A検討の白紙撤回を言い渡された、なんてことも普通にあります。こうなると「やっぱり資料出します」といっても後の祭りです。
本来まとめられるはずの案件なのに上手くいかなくなってしまう、というリスクを回避する点においてM&A業者の利用価値はあります。
実は、買手側から見たときの仲介会社の付加価値もまさにこういうところで、「売手がM&Aに変な偏見があると進めずらいから地ならししておいてほしい」というニーズは大きいです。
よくM&Aする買手というのは、M&Aのテクニカル的な部分について仲介会社のサポートは不要だと考えていることも多く、どちらかというと、売却案件の情報提供料や売主とのコミュニケーションの緩衝材としての価値として仲介手数料を払っていると考えてもよいと思います。
3.交渉の仕方が分からない
会社や事業を売却するとき、おそらくいくらで売却できるのか、が売主としての大きな関心事の一つだと思います。
では、金額交渉というのはどうやったらいいのか、についてはM&A特有の交渉方法などもあったりするので、これは経験値ゼロだと戸惑うことも多いはずです。
不動産の売却のように、まずは高めの売値を出して、あまり食いつきが良くなければ徐々に下げていく、というやり方でM&Aの交渉をしようとしている方がいますが、これはちょっと危険です。
買手としては、会社としてその投資案件にいくら出せるだろうという見方をし、どう考えても割高だと判断した場合、金額交渉に入ることもあれば、売手からは何の前触れも無しに検討見送りという結論に舵を切ることもあります。買手として検討するM&A案件は他にもあるというケースもあるので、高いのであれば他の案件にしよう、となってしまうわけです。
最初にハイボールを投げすぎたがために、具体的な検討に入る買手がいなくなってしまった、ということもあるので、財務状況からみた出し値の水準感、希望の伝え方、などは慎重に行わないと機会損失になってしまうというのがM&Aです。
M&A業者の作成する株価査定などを鵜呑みにするというのは違いますが、それでも、伝えようとしている希望条件が結構無茶を言っているものなのかそうでないのか、他の売却案件と比べた時に割高に見えるかどうか、といったことは、売主だけで判断するというのは難しいことが多いかと思います。
4.決断に踏み切れない
自力でM&Aを進めると、決断に踏み切れないケースも以外と多いです。
「今、売った方がいいのか分からない」
「この買手に譲るのが最良な選択なのか分からない」
結局は売主自身で決めないといけないのですが、初めてのM&Aで変な決断をしたくないという気持ちも強いはずなので、判断に迷いが生じて決断できないことも出てきます。
どの買手に会社や事業を譲渡すればみんなハッピーになれるか、なんて答えはありません。次々にお見合いをして、良いと思った時点でその人に決める(その先の相手は断る)、といったような決断が必要になってくるようなイメージなので、その買手と一緒になった時の絵が描けるかどうかを壁打ちできる人や、純粋に背中を押してくれる人が欲しいということもあると思います。M&A業者はそういう役割もあります。
逆に、M&A業者などいなくてもできることもあります。
例えば、資料収集などはM&A業者が代わりにやってくれるものではないので、結局業者を使おうが使おまいが自分でやることになります。また、法務アドバイスや税務アドバイスはM&A業者の業務外になるので、部分的に士業専門家の手を借りればM&Aできる、ということであれば、M&A業者に依頼せずに直接士業専門家を探すのが良いでしょう。
売手側は買手に対して企業概要書という資料を見せることで、M&Aをスムーズに進めることができますが、これもM&A業者でないと作成できない、というものでもないので、自力で会社や事業の内容、財務の内容をまとめて資料として作成することもできると思います。実際に自分で概要書作りました、という方も結構います。
M&A業者に全部丸投げすると楽ではあるのですが、役割として何を求めるか、を明確にすることでより自分に適した業者選び、時には、業者を使わない、という選択肢ができるようになるので、手数料の妥当性などもとらえやすく、後から後悔しないM&Aができるのではないかと思います。
当社では、自力では難しいところ、AIに代替できないところを中心にサポートをしておりますので、不要で過剰なサービスで手数料が高いのではなく、必要な時に必要なサポートを質を担保しつつ低価格で提供するという部分で、納得感のある支援を行っております。
弊社へのお問合せの際は下のお問合せフォームよりお問合せ下さい。
お問合せ
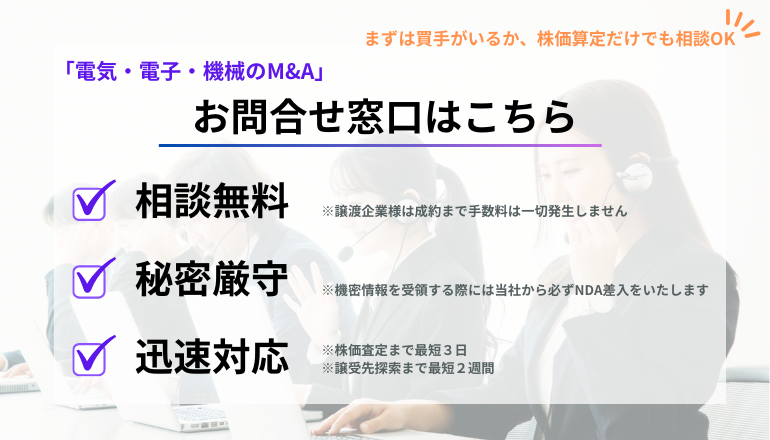
-2.png?1768980797)