ある日、取引先から呼ばれ、こんなことを言われたとします。
「おたくの会社とは長らく取引をしていたけど、申し訳ないが今後は終了したいと思っている」
こんな時まずどんな事を考えるでしょうか?
売上がどれだけ落ちるんだろう
従業員の仕事が無くなるから解雇しないといけないのだろうか
在庫は余剰在庫になってしまわないか
銀行からの借金は返せるだろうか
など、色々な不安がよぎることかと思います。
当社でもこういった状況に陥っている、もしくは、陥る可能性があるというお客様からのご相談をいただくことも多々あります。
このような場合に考えられる展開や打てる対策について過去事例をまとめてみますのでご参考いただければ幸いです。
主要な取引先との取引消失で実際起こること・対策
それでは、主要な取引先との取引が消失するとどのようなことが実際起こるでしょうか。
業界・業種にもよって起こる問題は異なると思いますが、多くの業界・業種で共通して起こる以下のような事象について取り上げてみます。
・収益力減少による借入金返済余力の不足
・余剰在庫の発生
・設備の余剰 など
以下に一つずつ解説していきます。
仕事量激減による従業員の余剰
人が介在しない事業やよほど柔軟な雇用形態でもしていなければ、取引が消失することは人手が余る可能性を意味します。
多くの会社で固定費において人件費の占める割合は高いので、売上が急減したことで固定費が賄いきれなくなり赤字に転落することも多いです。とはいえ、今まで一緒に働いてきた従業員を辞めさせるのは心理的にハードルが高いでしょうし、人材不足の昨今一度解雇してしまうと再度採用することが難しいため簡単に解雇という選択が取れないことも多々あると思います。
例えば、ソフトウェア開発業のような労働集約型で、かつ、新規の採用競争率の高い業種では、急激な仕事量の減少に対処するのが難しく固定費を圧迫し続けるということもよくあります。当社では仕事柄色々な会社の決算書を拝見することがありますが、この業種で債務超過になっている場合は、急激な仕事量減少でも雇用を確保するために運転資金を金融機関から借り入れるということを過去に行ったというケースも珍しくありません。
主要な取引先との取引が消失した場合は、仕事量を確保する、ということを考えなければなりません。
会社によっては他社の仕事を振ってもらう、他社で自社の従業員に働いてもらう、ということも対策としてあります。上記のソフトウェア開発業であればSESのようなものもありますし、運送業であれば庸車、製造業であれば期間工というようなイメージです。
ただし、労働者派遣法に抵触しないかなど留意しなければならない点もあります。
収益力減少による借入金返済余力の不足
事業を行う上で、運転資金や設備投資資金等を金融機関からの借入金で賄っている会社もあるでしょう。
こうした会社の場合、売上や利益が喪失したことにより借入金の返済が困難になることもあります。手元にキャッシュがある内は返済は継続できますが、キャッシュが無くなったときには返済自体が困難になります。
そうなるとキャッシュを確保するために、売上債権を早期に回収するよう取引先への交渉を検討するといったことや、キャッシュの出を減らすために経費を削減するといったことを行いますが、それでも返済が難しい場合には金融機関と交渉して返済をリスケジュール(リスケ)する必要も出てきます。
リスケすることで一時的に元金の返済を猶予して利息だけの返済に変更することなどもできるため、経営の立て直しのための時間が確保できることがあります。
ただし、注意しなければならないのは、金融機関側には返済を再開させるためのリカバリープランの説明を求められるといった点です。主要な取引先を喪失したとなれば他の新規の取引先を探すといったことがリカバリーになってきますが、比較的インパクトが大きい問題として捉えられる場合もあります。
また、リスケを行うことで金融機関側の融資先格付けが落ち、今後の新規融資額や融資条件などに影響が出る可能性があるという点も注意が必要です。金融機関は融資先に対して「正常先」「要注意先」「要管理先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」といった格付けを行いそれをもとに貸倒引当金の金額を決めていますが、一般的にはリスケを行った先は少なくとも「正常先」ではなくなるため、「要注意先」に格下げされたりします。近年、金融庁から金融機関に対して、会社の財務だけではなく技術力や知的財産、顧客販路などを総合的に判断して格付けするよう方針が示されていますが、取引先喪失は無形資産の喪失でもあり財務にも影響を与えるため金融機関の融資姿勢が変わることには注意が必要です。
取引先のバランスが偏っている会社の場合には、急激な業況変化に対応するために、普段使わなくても機動的に借り入れが起こせる当座貸越の枠を確保しておく・ファクタリングを申し込んでおくといったこともよいでしょう。経済全体を揺るがすような事態であればコロナ禍でのゼロゼロ融資のような融資商品が出ることもあるので、債務者に有利なものがあれば積極的に利用するのも有効な手段となります。
余剰在庫の発生
例えば、卸売業や製造業では、特定の取引先に対して納期遅延をしないように余剰在庫を持っているケースがありますが、取引先との取引が消失することでこうした余剰在庫がそのままデッドストックになることもあります。
引取責任がある在庫の場合は、取引終了と同時に余剰在庫を取引先で買い取ってもらえるということもあると思いますが、見込み発注をしていた分については宙に浮いてしまうこともあります。
こうした引取責任の無い見込み在庫は、市場で売却できるケースやメーカー等に返品できるケースもあるにはありますが、当然まずは取引先と交渉します。
交渉が難航した場合で、委託取引ではなく単なる売買取引の場合であり販売元の判断で製造・仕入れたものであった場合は、下請法のような弱い立場にある者を守る直接的な法律はないということもあり、民法や独占禁止法などによって主張する販売元もあるかと思います。
この問題については、普段から揉めないよう、納期が長い旨、余剰在庫を発注する旨、取引先向け専用に在庫を確保している旨及び取引が終了する際には前もって連絡をしてもらう旨などを取決めしておくに越したことはありません。仮に揉めた際の証憑にもなります。
設備の余剰
主要取引先のための専用設備を整えている場合には、その取引先との取引が消失した場合に設備に余剰が発生することがあります。
こうなった場合、通常はその設備を他の取引先向けのビジネスに転用できないか、あるいは、処分するということを考えることが多いと思います。
そもそも特殊な特定の取引先向け専用の設備であれば、導入する際に自社の資産にしないよう取引先がリース料を支払う形態にしたり、少なくとも償却期間中は取引保証をする契約にしたり、自社の負担が少なくなる補助金を利用したりといった形式に持っていく方がリスクが少ないところではあります。
ただ、もしこうした施策が無く、買取業者に叩き売るか廃棄するかという選択肢しかない場合には、M&Aという枠組みの中で、その設備を有効利用してもらうということも選択肢としてはあります。
M&Aの買手というのは事業を譲受するのが多い目的ではありますが、人材や設備といったリソースを獲得する手段として考えている買手もいますので、買取業者を介さず、その設備を有効利用してもらえそうな取引先にピンポイントで購入してもらう打診を行うことでより高く譲渡することもできることがあります。
主要取引先との取引が消失するリスクは非常に大きいため、日頃から「もし主要取引先との取引が無くなったら」を考えておくのが望ましいですが、それは分かっていながらも難しいこともあると思いますので臨機応変に対応を考えていく必要があります。
ちなみに、販売先との取引が急に無くなるケースというのは、以下のようなことも考えられるので、原因となる問題に対して考察した上で、リカバリー可能であれば改善すべきところを改善して取引を継続してもらうという手段を考えるのもよいでしょう。
・他社の方がコストが安いから
(QCDなどで条件が他社よりも劣っているから)
・販売元がトラブルを起こした
・担当者間の不和
【リカバリー不可能と思われる背景】
・販売先のエンド先の業況悪化、方針変更によるトレンドの変化
・販売先の財務状態の急激な悪化
従業員の雇用を守るM&A
それでは、主要な取引先との取引が無くなった、あるいは、無くなる可能性のある場合で、リカバリーすることが不可能な場合はどうしたらよいのでしょうか?
余剰となってしまった人員・設備・その他のビジネスについては、場合によってM&Aという手段で解決できる可能性はあります。
単純に事業を終了させる、ということであれば、人員を解雇して、設備を安く叩き売って、会社を精算するといった手続きになり、従業員の解雇が伴い経済的にも損をする可能性もあり、更に、剰余金が大きい会社を精算した場合、株主はみなし配当課税され、最大で55%程度の総合課税で徴税されるということもあるため負担が大きくなることもあります。
この点、M&Aであれば、その人員や設備を同じか比較的近い業態で活用してもらえるので、従業員の雇用維持・働きやすさに繋がることもあります。また、株式譲渡でM&Aできれば分離課税で税負担が減ることが期待できたり、事業譲渡でM&Aできれば取引先喪失により発生した本業赤字に益金(事業譲渡代金から簿価を差し引いた益金部分)を充てて法人税等を圧縮することも可能です。
但し、主要な取引先を失った会社のM&Aは譲受先を探すのは通常よりも困難です。
M&Aの検討には過去の財務状況を参考にリスク判断することも多いですが、直近で主要な取引先を失った会社の場合には、収支バランスも大きく崩れ、過去の数値が参考にならないこともあるので、買手が買収をしり込みすることもあります。保守的な買手であれば、業況が一旦落ち着くまで様子を見ようということになることもしばしばです。
こうした会社を買収するのは、業種やビジネスモデル、設備等で近いものを持っている買手であり、主要取引先との取引喪失で空いた穴を埋めることができる買手、と考えるのが王道ではありますが、詳しくは専門家も交え、実際のニーズを踏まえた買手探しをするのがよいでしょう。
当社では、電気・電子・機械領域でこうした部分的なリソースを探している買手企業との情報交換も盛んに行っておりますので、お困りの際は一度ご相談いただければと思います。
お問合せの際には、以下のお問い合わせフォームよりお問合せ願います。
お問合せ
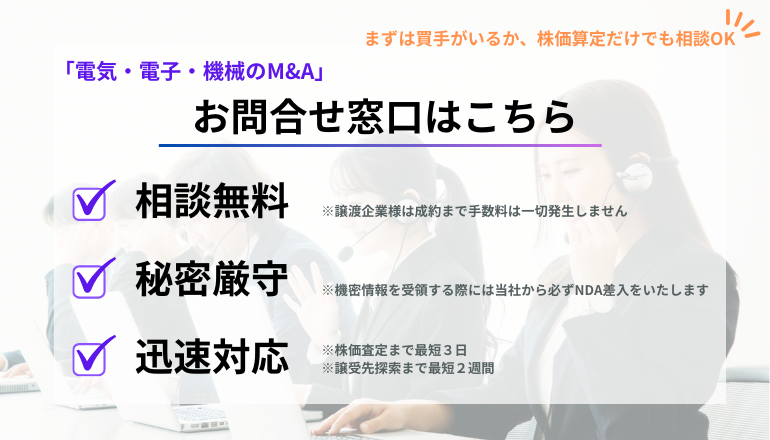
-2.png?1768912216)