これからM&Aしようとするエレクトロニクス関連企業様は、
「得意先の購買さんにM&Aするのダメって言われたらどうしよう」
という悩みが大きいのではないでしょうか?
あるいは、
「購買さんに相談してからM&Aを検討し始めるのが筋かな?」
と思う方もいるかもしれません。
中小企業のM&Aで上場していない株の取引をする場合は、売手と買手で協議をして話を固めてから取引先に報告する(契約内容によっては、最終契約締結~クロージングまでの間に許可を取りに行く)というのが一般的です。
つまり、M&Aが終わってからか、もしくは、M&Aのかなり終盤です。
「そんな終盤にして、許可してもらえなかったとしても大丈夫なの?」
と思われる方もいると思いますので、今回はM&Aで取引先の許可が得られないことで起こってしまう内容・M&Aを取り組む時にもっておくべき心構えについて説明していきたいと思います。
購買が反対したらM&Aはできない?
まず、重要な点として「購買(取引先)が反対したらM&Aはできない」かという点です。
結論からいうと、M&A自体はできます。
ただ、「売手は、買手から契約解除を受けるリスクがある」というのを注意しておかないといけない、ということになります。
基本的には、M&Aは売手と買手の契約になるので、この取引に第三者である取引先が異議を唱える筋合いにないという関係性にあります。
一方で、取引先は売手企業と取引をしているわけですので、取引先のご機嫌を損なうことで、取引先と売手企業との契約や取引に影響が出ることがあり、それが引いては買手からみた売手企業の価値に影響してきます。
そもそも、買手がそのM&Aをしようとしている目的が、例えば「現在の取引先との継続取引が見込め、そこに自社のリソースも投入することでシナジー効果が生まれそう」とか「現在の取引から生まれている利益が魅力的」という考えでM&Aを検討しているようであれば、取引先との取引に影響が出ることは、M&Aする目的が叶えられない話になってくるので、大幅がM&A取引金額減額や契約解除になる可能性も浮上してきます。
こういった買手の意向は、売手との最終契約書の中でも現れます。
その取引が無くなってしまうと影響が大きいようなものについては、最終契約書の中で、「クロージングまでの間に取引先から取引が継続できる旨の同意書を取り付けること」という条件が付せられることも多いです。
買手としては、取引先との取引が無くなろうが何が起きようが最終契約締結をしたら必ず株を買い取らなければならない、となるとそれはそれでリスクになってしまうので、取引の安全性を確保するために必要なわけです。
また、このような具体的な条項でないにせよ、「対象会社の資産、負債、財務状態、経営、収益性、事業計画又は事業に対して重大な悪影響を及ぼす事由が生じていないこと」というような包括的かつ抽象的な内容でクロージングの前提条件を交渉されることもあるので、売手としては注意しつつ対応する必要があります。最後の最後まで気が抜けないというのが実際のところです。
実際の事例でも、売手と買手との間でM&Aの諸条件がまとまり、いよいよ取引先への通知、となった際に、取引先から猛反対を受けてしまいM&Aが頓挫してしまったという事例はあります。最終的には諸条件を見直したり、取引先への説明を尽くしながらM&Aをまとめる方向で動きましたが、買手側の考え方によっては取引先に猛反対されたことでM&Aを白紙にするということもあったでしょう。
取引先が猛反対するというのは様々理由があるものですが、現オーナーが代表をしていたから取引していたという属人的な理由や、取引先側の事情(取引先口座数を増やしたくないなど)もあります。こればかりは通知してみないと分からない不確実な部分もありますが、できるだけ事前に客観的な情報を収集しつつ、M&Aプロセスを組み立てることが重要です。
とはいえ、そもそも取引先の許可の有無がM&Aに与える影響は、本当にケースバイケースです。
例えば、全売上の内95%を占める取引先との取引継続ができなくなれば会社が傾くレベルの話になり得ますが、全売上の内5%を占める取引先で、利益も出ないような取引先については取引継続できなくても大勢に影響はないと判断する買手もいます。
また、M&Aの目的が取引先ではない場合(例えば、物流施設・製造設備や従業員に魅力があり、取引先が剥落しても、買手の取引先との取引を広げられる、など)、買手のリカバリー案がある場合には、M&A自体を実行できるケースもあります。
M&Aは、その取引先が売手企業にとってどういう存在なのかを客観視する機会でもあり、予め自己分析した上で、買手を探すことができれば、成約できる可能性を高められることにも繋がります。
ちなみに、こういう話をすると、
「じゃあ、M&Aをする前に取引先に許可をもらおう!」
という方もいると思います。
これは、M&Aをする前に従業員にM&A検討する旨を伝えておこう!というケースとも近いのですが、必ずしも全て義理立てして進めることが必ずしもベストとは言えない(単に売手のリスクになってしまうこともある)ので注意しましょう。
まだ具体的に買手も決まっていない状態で「弊社はM&Aで売却することを検討しています」なんて言ったら、それを言われた取引先の購買担当は、「この会社大丈夫か?供給性を確保するために代替できるようなサプライヤーを探しておくか」という動きに出るかもしれませんし、それを聞いた従業員は「うちの会社ヤバいのかな?給料も下がるかもしれないから、転職活動しようかな」という動きに出るかもしれません。
もちろん買手としては、取引先もM&Aに同意してくれており、従業員もM&Aに同意してくれている、という方が不確実性がなく望ましい状況ではありますが、失敗した時に売手だけがリスクを負うという話になるので、売手側はこの関係性を理解した上で判断を下すべきです。
「M&Aを検討する」という情報は、会社にとって重要な話なので関係する人には伝えないといけない情報というだけでなく、不安も与えてしまう可能性がある情報であることは認識した上で行動に移す必要があります。不確実な情報で不安を与えるよりも、きちんと説明までできるところまで話を詰めてから伝えるというのも誠実な行動という考え方もあるのです。
途中でM&Aが白紙になると着手金は無駄になる?
途中でM&Aが白紙になってしまった場合、無駄になるコストはあるのでしょうか?
実は、このコストについては売手側はそれほど負担が無いケースが多いです。
そもそも売手側がM&Aをする場面において自ら捻出するコストというのは、例えば以下のような費用になります。
・士業に関する費用(弁護士報酬、税理士報酬など)
・実費(旅費交通費など)
・その他(不動産鑑定、組織再編費用など)
昨今では、完全成功報酬型のM&A専門家も増えてきているので、M&Aしない場合は0円というケースもあります。
例えば、弊社の場合も売手側はM&Aしない場合は0円です。M&A専門家の中には、着手金や中間金が発生するところもありますし、完全成功報酬ではあるものの成功報酬発生基準がM&A成立ではなく最終契約締結というところもあるので、クロージング要件が満たせず破談になるとM&Aしないのに成功報酬を払わないといけない、というケースもあるので業者選びのタイミングでよく確認しておく必要があります。
士業の費用も、どのような士業かにもよりますが、M&A専門家ほど費用がかからないことがほとんどですし、交通費などはそれほどの額となるケースは少ないでしょう。不動産鑑定や組織再編が必要になる案件もある程度限られるので、必ず発生するコストというものではないです。
金額的に大きいのは、M&A専門家への着手金や中間金などかと思います。
これらのコストはM&A専門家に支払うコストで、M&Aが白紙になり、M&A専門家との契約(仲介契約など)が終了になると返金されずに無駄になってしまうことがあります。成約未成立時に返金されるか否かをきちんと契約書上で確認しておくことが重要です。
なお、売手の感覚としては、M&A交渉終盤で買手から値下げ交渉を持ち掛けられた場合に、着手金や中間金を無駄にしたくないからという心理的なバイアスがかかり、値下げ交渉を飲んでしまうということもあり得ますので、この点も留意しつつ、M&A専門家を検討するのがよいかと思います。
ちなみに、売手側はそれほど金銭的な負担が無いからといって気持ちが固まっていない中でM&A検討を進めるのは控えましょう。
合理的でない理由で一方的に交渉の中断を申し出られる売手の方もたまにいらっしゃいますが、買手が買収監査をすればコストがかかることから、そのコスト等を損害賠償として請求されるケースもありますし、M&A専門家の中にも、合理的でない理由で交渉を中断された場合には人件費等を請求する、という契約のところもあるからです。
「当初希望していたのが〇円だったのにどの買手もそれに満たない提示額だった」ということであれば仕方無いですが、「業績が良くなってきたので、やっぱり会社を売却するのを辞めたい」というようなものは、合理的でない一方的な交渉中断、と見做される可能性があります。
会社によって最適な進め方は違う
取引先にM&Aをする意向を伝えた時に、どういうリアクションになるかは分からないものです。
万全に準備をして、適切な伝え方をしたとしても、不測の事態が起こることはあります。
問題が起こった際にどう対処するかまで事前に売手と買手の間で認識合わせができていれば、そのような場合においても冷静に対処できることもありますし、お互いがどういうリスクを負っているかを正しく理解しているのであれば、最悪のケースでもトラブルになる可能性を低くすることができます。
M&Aを進める中で当事者のトラブルが起こるのは、どちらかに錯誤があり、「相手の為を思ってやったのになぜ私だけが損をするのか」という心理的なもつれも原因であったりします。
M&A専門家を使うメリットというのは、こうしたM&Aプロセスにおいてその判断の先に起こり得る問題点や、抱える可能性のあるリスクについて、先回りで教えてもらえるという点があります。
そして、担当コンサルタントを選ぶ際にも、成約件数が多ければ多いほど、交渉終盤でどのような問題が発生し、どう乗り越えたか明確に伝えてくれる可能性が高くなるかと思いますので、そのコンサルタント自身が身をもって経験した話を、M&A専門家を選ぶ段階で聞けるとより安心感をもって進められるのではないでしょうか。
弊社では、譲渡企業様におかれましては、購買担当者様(取引先様)にNoといわれたことでM&Aが成立しなかった時には手数料が発生しないという安心の報酬設定になっております。また、成約件数数十件以上のコンサルタントで担当させていただくことをお約束しておりますので、事前のリスク洗い出し含め高品質なサービスをご提供させていただきます。
あるいは、購買担当者側との調整から入るこういったサービスも提供しておりますので、円滑・円満にM&Aするためにご検討いただくのもよろしいかと思います。
ご相談、ご質問等ございましたら以下お問合せフォームよりお問合せいただけますと幸いです。
お問合せ
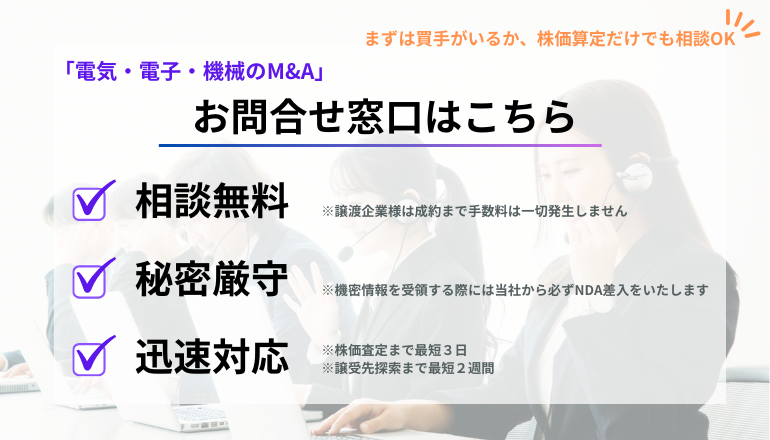
-2.png?1764546453)
