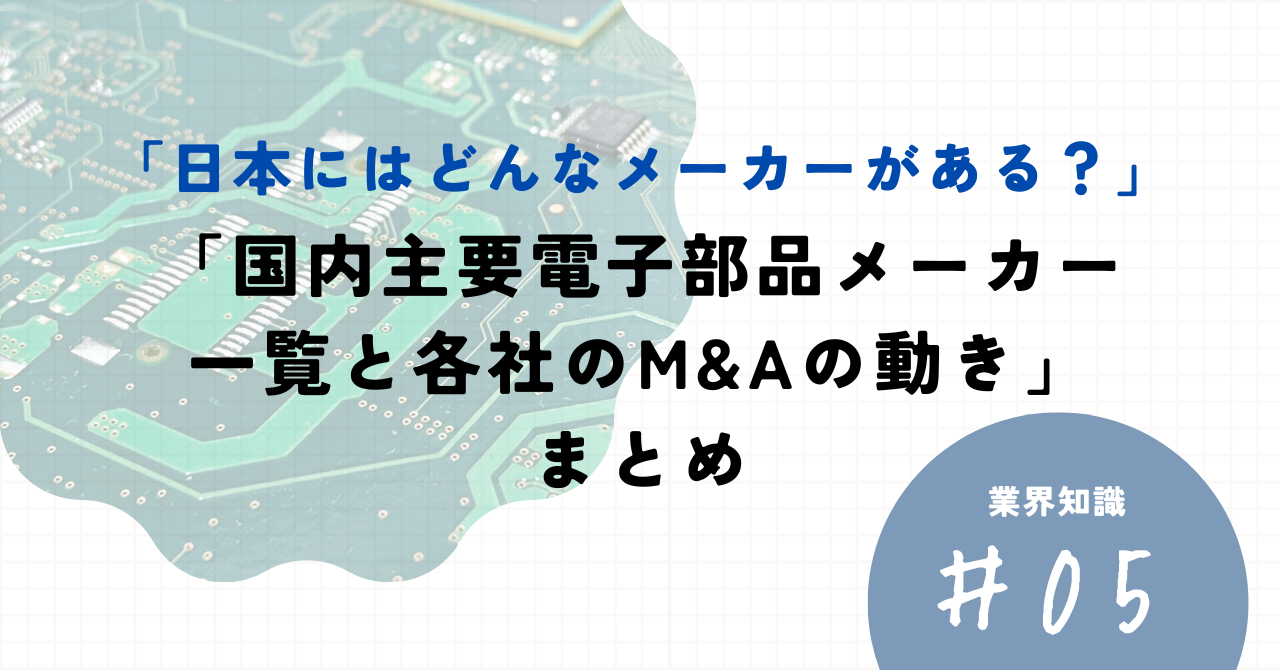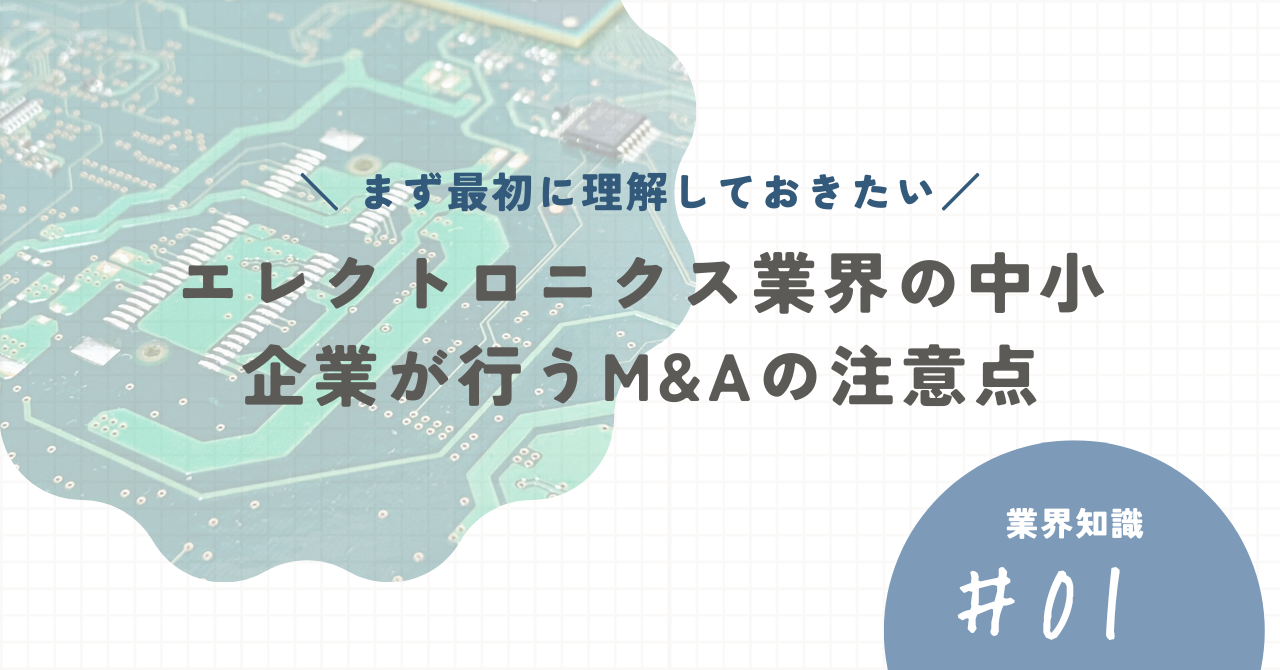国内の半導体・電子部品商社は、二次商社や三次商社を含めると日本全国に1,000社程度存在すると言われています。
近年では、一次商社間の大型M&Aも注目を集めていますが、世界的にみると日本はかねてから半導体の直販比率が低いと言われており中小規模の商社が多いことと、昨今そのような中小企業の事業承継問題なども追い風になり、まだまだM&Aが加速するように思われます。
今回はそのような半導体・電子部品商社の一部を取り上げ、どのくらいの規模のどういった会社があるのか、また、そういった企業がどういったM&Aを行っているか調べてみました。
当サイトは、中小企業のM&Aを主題にしているので、今回は少し大きい話になってはしますが、電子・電機分野の企業においては部品供給面において影響が大きい部分ではありますので、参考にしていただけると幸いです。
国内の主要電子部品商社まとめ
国内の主要な半導体・電子部品商社を以下にまとめます。
半導体関連をメインで挙げておりますが、半導体商社の中には、半導体装置製造を行っていたり、総合商社の一部門であったり、他のソフト面や異業種の運営を行っている会社も多くありますので、数あるうちの一部という理解でご覧ください。
■国内主要電子部品商社
| 会社名 | 売上高 | 従業員数 | 概要 |
|---|---|---|---|
| マクニカ | 1兆292億円 2023/3期 | 4,203名 2023/3期 | 海外メーカーを多く取り扱う独立系半導体商社。セキュリティ関連にも強み。半導体商社・セキュリティ関連企業へのM&Aの他、医療システム・AI関連への投資も行う。 |
| 加賀電子 | 6,081億円 2023/3期 | 8,092名 2023/3期 | 半導体の販売の他、EMS事業、PC関連機器の販売、アミューズメント関連商品販売なども行う。 |
| レスターホールディングス | 4,871億円 2023/3期 | 2,601名 2023/3期 | UKCホールディングスとバイテックホールディングスが前身。PALTEK、都築電気傘下の会社とも資本提携。 |
| トーメンデバイス | 4,176億円 2023/3期 | 187名 2023/3期 | 豊田通商が50.1%(2023/3期)の株式を持つ半導体商社。丸文セミコンからも事業移管受ける、韓国のサムスン電子の製品を販売するメーカー系半導体商社。 |
| リョーサン | 5,079億円 2023/3期 | 954名 2023/3期 | 三菱電機などを主要取引先とするルネサス半導体の販売が強い商社。2024/4に菱洋エレクトロニクスと経営統合し、リョーサン菱洋HDを設立予定。 |
| 菱電商事 | 2,603億円 2023/3期 | 1,008名 2023/3期 | 三菱電機が35%超の株式を保有(2023.3.31時点)する三菱電機グループのメーカー系専門商社。半導体のほか、FA機器や空調機器、農業関連事業も行う |
| 東京エレクトロンデバイス | 2,024億円 2023/3期 | 1,318名 2023/3期 | 年商2兆円超の半導体製造装置メーカー東京エレクトロンが33.8%(2023.3期末)を持つ持分法適用関連会社。自社グループ企業への製品供給も行い、産業機器向け・車載機器向けの供給が多い。 |
| エレマテック | 2,398億円 2023/3期 | 1,184名 2023/3期 | 高千穂電気と大西電気が合併してできた会社。豊田通商と資本業務提携を締結。豊田通商が58.6%保有する子会社。 |
| 伯東 | 2,336億円 2023/3期 | 1,223名 2023/3期 | 半導体の他、ケミカル関連の事業も強みを持つ商社。海外製半導体デバイスを扱うマイクロテック社と資本提携。 |
| 立花エレテック | 2,273億円 2023/3期 | 1,381名 2023/3期 | FAシステム関連事業も行う半導体商社(売上構成はFAシステムの販売50%程度、半導体デバイスの販売が40%弱程度)。仕入ベースでは三菱電機及び三菱電機グループ、ルネサスが多い。 |
| 丸文 | 2,262億円 2023/3期 | 1,117名 2023/3期 | 民生機器、自動車向けの販売が多い。サムスン電子製品の販売に関する事業の譲受(H23年)・譲渡(H30年)をトーメンデバイス(旧UKCHDグループ)と行っている。 |
| 萩原電気ホールディングス | 1,860億円 2023/3期 | 697名 2023/3期 | ルネサステクノロジとNECエレクトロニクスの経営統合により、ルネサステクノロジ特約店の新興電気のルネサス代理店事業を譲受。 |
| 新光商事 | 1,791億円 2023/3期 | 666名 2023/3期 | 日本TI事業をKTLに事業譲渡。 |
| 三信電気 | 1,611億円 2023/3期 | 567名 2023/3期 | |
| ネクスティエレクトロニクス | 豊田通商が100%保有する子会社 |
概ね年商順にしておりますが、「トーメンデバイス」「エレマテック」「ネクスティエレクトロニクス」は豊田通商グループですので、一体としてみるとその存在感はより大きいようにみることができます。
半導体商社は、特定のメーカーを中心に扱うメーカー系の半導体商社と特定のメーカーなどと資本関係も持たず独立して様々なメーカーを取り使う独立系の半導体商社があります。
以前以下の記事でも紹介しましたが、国内半導体メーカーだけでも供給している製品群が重複しているケースはよくあります。
場合によって、半導体商社が取り扱っているメーカー同士で製品群が競合状態になるため、特定の製品群については特定のメーカーだけを取り扱う商社もありますし、独立系半導体商社の中でも、競合している製品群のメーカーを忖度なく取り扱うために、分社化したり、会社内でカンパニー制を取るケースなど様々です。
売上の金額規模はかなり大きく、1兆円を超す半導体商社もあります。半導体の中でも1チップ当たり数円未満のものから数十万円超のものなど幅もありますが、単価としては安くても、販売先の製品に搭載され大量に使用されるようになることで売上が見込める事業へとなります。
大手半導体商社では、半導体の卸売だけではなく、セキュリティ関連の事業を行っていたり、EMS事業や、電気機器などの販売事業を行うケースもあります。また、東京エレクトロンデバイスのように、半導体製造装置事業を行う一方で、自社供給分も含め半導体の販売を行う会社も存在します。
半導体・電子部品商社のM&A
半導体・電子部品メーカーのM&Aはこれまでも積極的に行われています。
大手半導体メーカー同士の大規模M&Aも行われていることもあり、大手半導体商社はじめメガディストリビューターを目指す動きがあります。
日本市場は自動車業界や産機業界中心に手厚い品質サポートや技術サポートなどが求められますし、多層に渡るサプライチェーンがあるため小回りの利く半導体商社にも存在感があるという事情もありますが、海外では直販が多い半導体業界において、メーカーに対する存在感を出すために商社の巨大化も進んでいると言えます。
大手半導体・電子部品商社のM&A事例としては、例えば以下のようなケースがあります。
・グローセル社(米・半導体商社)
・Answer Technology社(台・電子部品商社)
・富士エレクトロニクス社(日・半導体商社)
・株式会社ナイスメッツ社(日・ヘルスケア)
・S&J社(日・ネットセキュリティ)
・CrowdANALYTIX社(インド・AIプラットフォーム)
・Save Medical(日・医療機器システム設計)
・Netpoleon(シンガポール・ネットセキュリティ)
・iSecurity(台・ネットセキュリティ)
・エクセル(日・半導体商社)
・富士通エレクトロニクス(日・電子部品商社)
・サイバーフロント(日・ゲーム開発事業)
・東京電電工業(日・電気通信工事業)
・ADM(日・半導体商社)
・エスアイエレクトロニクス(日・アミューズメント機器装置開発)
・ワークビット(日・LSI開発)
・都築電気傘下の国内外4社(日・半導体電子機器部品販売)
・WPG Holdings(台・電子部品商社)
・タックシステム(日・音響システムの設計構築)
・PALTEK(日・半導体商社)
・菱洋エレクトロニクス(日・半導体商社※2024/4経営統合)
・プリケン(日・プリント配線基板の設計・製造)
・八州電子ソリューションズ(日・電子部品商社/ソリューション)
・大電社(日・FA機器販売)
・マイクロテック(日・海外製半導体商社)
・大崎エンジニアリング(日・センサーデバイス関連装置製造販売)
・新興電気(日・ルネサス代理店事業の電子部品販売事業)
半導体商社においては、自社が扱っている半導体メーカーと同じか親和性の高いメーカーを扱っている商社同士のM&Aが行われる傾向もありつつ、巨大な半導体商社においては自社グループ内で全方位的に商材を扱えるような戦略で動いている商社もあります。
メーカーの親和性という点では、マクニカが2015年に行った富士エレクトロニクスとの経営統合を見ても、両社で共通している主力取扱メーカーとして「アナログ・デバイセズ」「テキサス・インスツルメンツ」「インフィニオン」などがあり、商材としての親和性がありながらも、マクニカが大手顧客も多く有する一方、富士エレクトロニクスは中堅・中小顧客を多く有するなど、顧客層に違いがあることから、広い顧客をカバーできるようになるという目的もありM&Aが実施されています。
また、関連事業との親和性という点も大手商社のM&Aでは注目されます。
加賀電子が業界2位に浮上したきっかけとなった富士通エレクトロニクスとのM&Aですが、加賀電子は元々商社ビジネスだけでなくEMSビジネスも盛んであり、このM&Aを通じて富士通セミコン製品の取り込みだけでなく、商社事業からEMS事業へビジネスを展開させ、売上のみならず利益も拡大していこうというビジョンもみられました。
リョーサンがプリント配線基板の試作品の設計・製造をおこなっているプリケンへの第三者割当増資引き受けによる出資についても、非商社ビジネスの展開という観点で出資が行われており、試作品という技術的な知見が差別化要因になるという狙いもあったようです。
一方、商社においてはメーカーの統合の影響でM&Aが行われるというケースもあります。
萩原電気ホールディングスはNECエレクトロニクスの特約店でしたが、ルネサステクノロジとNECエレクトロニクスが経営統合し、ルネサスエレクトロニクスが誕生した影響もあり、商流の移動が生じ、元々ルネサステクノロジの特約店であった新興電気からルネサスエレクトロニクスに関する営業を譲受しています。
メーカー事情で商流が変動するリスクは商社として常に抱えている部分はあるので、いざ商流変更が起こった際に、自社が譲り受けられる立場になるよう、より多岐に渡る商流(買収する側のメーカー)を確保し、その商流の中でもきちんと実績を残しアクティビティを見せることが特に一次半導体商社においては重要な戦略となります。
中小企業のM&A
近年日本国内で増加傾向にある中小企業のM&Aですが、中小の半導体商社のM&Aも盛んに行われています。
上記のような半導体メーカーや大手の半導体商社の経営統合などの影響もありますし、社内的な事情として、後継者不在や先行き不安からM&A検討をするケースも多いです。半導体の歴史を考えると会社によっては既に2代目以降に経営権を移している一族経営の会社もありますが、どのような会社でも必ずしも経営者になりたい親族がいるとは限りません。
半導体という商材は非常にリードタイムが長いため、運転資金を確保することも重要ですし、場合によってはそれを借入によって賄うケースも多いでしょう。半導体業界のみならず中小企業のM&Aの譲渡理由について「借金を子どもに継がせたくない」というお考えの経営者様も多く、第三者が譲受先になり資金面の不安を解消する形でのM&Aも多くみられます。
事業を継続しつつ、従業員の雇用を維持し、創業者利益の面でも経済的な合理性を追求できるM&Aというのは今後も盛んになっていくと思われます。
もし、実際に中小企業の経営者様がM&Aを検討する際には、自社の事業と親和性のある会社様を譲受先として探す必要があります。単に会社全部をM&Aで売却するというだけではなく、商流毎に整理するなども有効なケースもあるでしょう。
譲受候補先企業には提案段階で、M&A後の展開も踏まえた提案ができるとその先に進む可能性が高くなるということもありますので事前準備をしっかりした上で検討をされることをお勧めいたします。
当社では、半導体・電子部品業界を専門に扱うコンサルティングや、セットメーカー様向けに仕入先移管や集約に関するサービスも提供しておりますので、エレクトロニクス業界でM&Aをご検討の方、仕入先の整理をご検討の方はまずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。
譲渡企業様については、M&A検討を始める前に注意しておかないといけないこともありますので、こちらの記事もご参考ください。
お問合せの際には以下のお問合せフォームよりお願いいたします。
お問合せ
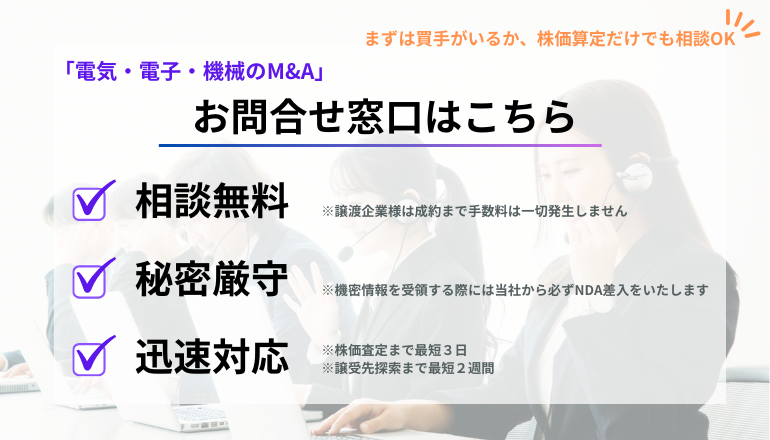
-2.png?1764546513)