セットメーカーの資材担当者様・購買担当者様に多いですが、電子部品を調達するときにこんな疑問を持つ方がいらっしゃいます。
「同じメーカーを扱っている仕入先であれば別にどこで仕入れても問題ないの?」
これは基本的には問題ないとは言えます。
ですが、色々と注意しておかないといけないこともあります。
当社では元々電子部品商社で実務をしていた経験から、こういった仕入先変更についてのコンサルティングも行っております。
ここでは電子部品の販売の仕組みや、仕入先を変更する際の注意点についてお伝えしたいと思います。
電子部品ってどこでも同じものが買えるの?
電子部品は抵抗、コンデンサ、トランジスタ、ICなど様々ありますが、例えば、ムラタの積層コンデンサを仕入れるケースを考えます。
開発部から依頼された部品表に「DE1E3RA102MA4BN01F」という型名のコンデンサが記載されているとします。
この時、この「DE1E3RA102MA4BN01F」は特定の電子部品商社A社からしか仕入れられないか、というとそういうわけではありません。ムラタのコンデンサを扱う商社が色々あるなら、他の代理店であるB社からでもC社からでも仕入れられます。
また、正規代理店でなくとも、2次以下の代理店という位置づけの電子部品商社もありますし、いわゆる市場在庫といわれる市場も存在しますので、そういったところから調達することができます。
なので、よほどのことが無ければどこからでも同じものが買えるわけです。
じゃあどうやって仕入先を決めているのか、という話になりますが、一例としてはこういう判断をしている会社もあります。
・試作に使うくらいの少量であれば、上記商社から無料サンプルを貰う
・商社との繋がりが薄ければ、少量なら市場在庫などで仕入れ、量産化したら相見積して安いところから仕入れる
・量産して大量に使用する場合には、値交渉してプロジェクト単位の特価を取得する
電子部品は製品によってミニマムのロットも大きいことがあるので、単価というよりも調達する量によって調達先を選ぶケースがあります。基板に数個、試作で10基板しか作らないのに数千個のリールで納品されてももったいないですので。
資材担当者様・購買担当者様として求められるのは、「納期は必達」「できるだけ安く」「品質サポートもちゃんとやってくれる」というあたりかと思いますので、基本は調達する会社の都合で最適な選択をすればよいということになります。
注意が必要なケース
ただし、電子部品の調達方法については色々と注意すべきことがあります。
メーカー毎で価格の決め方は異なる
できるだけ安い金額で購入したい調達側としては、商社に「できるだけ安くして!」と交渉することになりますが、メーカー側の価格の決め方や考え方を理解しておくことでスムーズにいくこともあります。
多くの電子部品メーカーは、標準品については製品毎にプライスリストなるものを用意しており販売代理店と共有しています。それは仕切値を意味するので、販売代理店はそこに色々な販売コストを考慮してマージン設定をし、販売価格を決めます。
よって、同じ電子部品メーカーを取り扱う商社間でも、マージンののせ方次第で仕上がりの販売価格が異なる場合があります。そういう仕組みを利用すると、例えば「セットメーカーの〇〇社の販売権は無いけど、プライスリストベースでマージンを削り、他の商社が販売している単価よりも安くして販売権をぶんどってしまおう」といった営業戦略も有効だったりもします。
特価扱いには注意
電子部品の販売においては、プライスリストよりもかなり安い「特価」という売価が設定されることもあります。
これは商社ではなく電子部品メーカー側が、エンドユーザーに採用してもらうために適用する特別価格のような扱いになるので、電子部品メーカーへの交渉が必要になります。当然ですが、量産時に数が出るアプリケーションに採用されるとか、他メーカー製品と互換性があり置き換えられてしまうといった事情があればあるほど交渉しやすくなります。
既に特価が適用されている製品の調達コストを安くするのに、他の商社に見積を取ってもあまり意味が無いです。
見積をする側の商社としても、プライスリストベースでは設定できない販売価格なので電子部品メーカーと交渉する必要がありますが、メーカー側としては「この特価は他商社の〇〇で取られた特価だけども」という話になりややこしくなるからです。
開発部で採用する段階で特価交渉されていることもありますので、事前に整理しておくことが望ましいです。
ロット条件は合わせること
電子部品を調達する際、製品毎のMOQ(Minimum Order Quantity)を考える必要があります。
今まで梱包形態をチューブで仕入れていたのに、リールの見積もりを取ったら安くなったとしても、歩留りの関係で滞留在庫になるならコストダウンにはなりません。逆に、チューブの方が少ないMOQで発注できるとしても、チップマウンターにそのまま装着できずリールに巻き直しているならそのコストも考える必要があります。
通常、梱包形態の違いでも型名に違いが出るので、見積間違いはないとは思いますが注意しましょう。
なお、梱包形態でによってプライスリスト上の仕切値が異なるケースもあるので、量産後思ったよりも物量が出ているとかで使用量が増えたり、同じ製品を他のアプリケーションでも横展開したため物量が増えたといった動向に注目してリール品へ切り替えしてコスト削減するという手法もあります。
品質・技術サポートは無視できない
いくら安いからといっても、問題が起こった時に対処してくれないというのでは困ります。
不具合が出た時に不具合解析してくれないと、製品の不良についての原因が分からないこともあるでしょうし、特殊な製品を使いこなすのに電子部品メーカー側の技術者と対等に話ができる技術者のサポートが必要になることもあるでしょう。
通常、製品自体が複雑になればなるほどこうしたサポートが必要になってきます。
ただ、実際のところ、そもそも電子部品メーカー側のサポートがひどいこともあるので、その場合はどの商社が対応してもイマイチな製品になります。こういう評判的な情報は、商社も身に染みて分かってはいますが、代々資材部・開発部で受け継がれていたりもしますのでメーカー毎のクセを掴んでおくといざという時に痛い目に遭わなくて済みます。
標準品ではないものには注意
電子部品の中には標準品ではないものも存在します。
極端な事例にはなりますが、例えば、1年でごくわずかしか動かない地殻変動を検知するためにジャイロセンサーを地面で埋め込むようなIoT機器を開発し、極めて高精度の高いミリタリーグレードのジャイロセンサーを採用した場合などです。
超高精度のものになると電子部品メーカーとしても標準品としては販売していないこともあります。ユーザーが限定的なのと歩留りの関係もあるからです。こうしたものの価格は特価の扱いに近いメーカー交渉品として扱うこともあります。
仕入先を変更してコストダウンできる?
結論から言えば、電子部品について、前述のような注意点はあるものの仕入先を変更してコストダウンすることは可能です。
ただ、あまりコストだけで乗り換えると結果高くつく、というケースもあるので気を付けないといけません。
せっかくコストが下がったのに、品質サポートが十分に受けられず品証からクレームが来ることもあるでしょうし、すぐに製品が生産終了になってしまい置き換えが発生してしまうなんてこともあるでしょう。
仕入先変更の際には開発部、品証部など他の部署とも連携しながら戦略的に進めましょう。
当社では、そうした注意点も踏まえつつ、セットメーカー様は完全無料で円滑な仕入先変更をサポートするコンサルティングも行っておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
お問合せの際には以下のお問合せフォームよりお願いいたします。
お問合せ
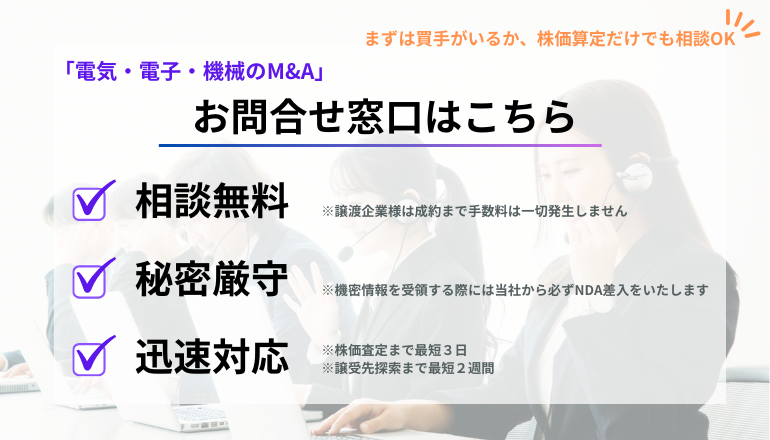
-2.png?1768471424)
